【好きなアルバムについて語る】Garbage - Bleed Like Me

2005年リリースの、アメリカのバンドGarbageの通算4枚目のスタジオアルバム。1stアルバム『Garbage』(1995)でデビューしてからちょうど10周年の節目にリリースされている。
このバンド、2020年11月現在サブスクに上がっている作品が何故か非常に少なく、本作もSpotifyなど主要サブスクリプションサービスでは聴くことが出来ない(Deezerには何故かあるっぽい。何でや)(※2021年6月追加:7thアルバム『No Gods No Masters』リリースとほぼ同時にサブスク解禁)。さっき調べたらiTunes Storeにも無いし。まぁ確かに日本国内の知名度は決して高くはないけど、ブッチ・ヴィグがドラム担当してる事もあって本国アメリカじゃバッチリ知名度も売上もあるってのに。それともこれって日本のストアだけ?海外のストアではちゃんと配信されてるの?情報求む。
まぁ別に、外タレが本国ではバカ売れしてるのに日本での知名度が信じられないくらい低いってのはよくある話で、特に90年代以降顕著である。逆に言えば90年代グランジ・オルタナ勢で日本でもちゃんと売れたのなんてRed Hot Chili PeppersとNirvanaくらいで、てかそれ以外いたっけ?ってレベルなので、正直今更目クジラ立てる程のことでも無いのだけれど、この時代に好きなバンドが多い自分のようなリスナーは、やはり皆悶々としているんじゃなかろうか、といつも思っている。
ちなみに2000年代以降もこの傾向は続いていて、KornとかSlipknoTとかの分かりやすいバンドはある程度売れてるけど、正直それくらい。あとはFall Out Boyが前回の単独来日でやっとこさ武道館やってたけど。IncubusとかPanic! At The Discoとかの本国では誰でも知ってるようなビッグネームですら、日本では新木場も埋まらないという状態。
対照的にイギリス勢は90年代以降Oasisを筆頭として、その後の時代のColdplayやMuseなども含め、どれもつぶ揃いにちゃんと売れている。てかThe Stone Rosesが武道館やれる位売れてるなんて知らなかったし。夏フェスへの出演頻度なども米オルタナ勢とは比べ物にならない程。英米でこれだけ差が生まれたのは、まぁ結局のところロッキングオンなどのメディアの力の入れ具合の違いとかもあると思うけど、米オルタナ勢より英ブリットポップ勢の方が総じて曲が親しみやすいっていう点も大きく影響していると思われる。日本人の感性って割とヨーロッパ寄りらしいよ、知らんけど。まぁBabymetalも最初はヨーロッパ圏で人気出たもんな。
…大分話が逸れた。

Nirvanaの『Nevermind』(1991)や、Smashing Pumpkinsの『Siamese Dream』(1993)などを手掛け、スティーブ・アルビニと並び90年代を代表するプロデューサーとしての名声を獲得していたブッチ・ヴィグが、「そろそろ俺もバンドやるで!」と言って結成したバンドがGarbageである。先程上げた2枚はどちらも大ヒットし、90年代グランジ・オルタナティヴムーヴメントを代表する作品として数えられている為、「あのブッチ・ヴィグが組むバンドなんだから、きっとNirvana以上にガチガチなオルタナ志向なのかな?」という期待と共に注目されたが、いざフタを開けてみると、ギターよりも電子音を全面に押し出し、ちょっと打ち込みっぽいスクエアなリズム、更にそこでコケティッシュな女性シンガー、シャーリー・マンソンが歌うという、所謂グランジ・オルタナとは真逆のポップなサウンドであり、大衆を驚かせた。しかもブッチ・ヴィグ、担当楽器はドラムである。いやお前ドラムなんかい、と誰もが思った筈。ちなみに俺は思った。
そのサウンドは、確かにアクの強さはあるものの、当時のメインストリームと比較すると非常にポップで、しかも結成したのはあのブッチ・ヴィグという事もあって、とにかく浮いていた。だがこの「ポップ」と「とにかく浮く」という点こそが、ブッチの狙いそのものであった。
Garbageがデビューした1995年は、カート・コバーン死後の次のリーダーが求められていた時期でもあり、同時にオルタナティヴ・ロックというジャンルそのものが停滞を始めていた頃でもあった。元々は80年代アメリカのメインストリームであった商業ロックなどに対抗する(Alternative=取って代わるものという意味がある)、商業性よりも音楽的実験性やよりリアルな表現、かつてのロック・パンクが持っており80年代ヘアメタル勢が持っていない緊張感などを重視したロックとして、アンダーグラウンドから広がっていったジャンルであったオルタナティヴ・ロックは、1991年のNirvana『Nevermind』とPearl Jam『Ten』のヒットによって一気に広がり、MTVを通して全米のお茶の間へ広がっていく。まぁ分かりやすく言うとモテモテのパリピ共を横目に見ながら軽蔑してた陰キャ共が、ある日を境に急にモテるようになってしまった、みたいな感じである。最初こそようやく掴んだ成功や、自分達が時代を乗っ取った優越感に浸っていたが、元々主流に逆らう為に作った音楽が主流になってしまった、反商業的スタンスで作っていた音楽が売れてしまった、というパラドックス的現実に気付き始めると、多くのアーティストが方向性に迷い始める。
「前作までの自己模倣はしない」「より反商業的に」「売れればセルアウトと叩かれ」「でもある程度売上は必要」という縛りを課された(或いは自ら課したのか)オルタナバンド達。冷静にコレ無茶振りが過ぎるとしか思えないんだけど、それでも彼等は苦悩しつつ創作に励み、Nirvanaが『In Utero』(1993)、Pearl Jamが『Vitalogy』(1994)、Nine Inch Nailsが『The Downward Spiral』(1994)、Smashing Pumpkinsが『Mellon Collie and The Infinite Sadness』(1995)などの傑作を次々とドロップ、ヒットチャートへ送り込んでいく。だがこの方法論では、アルバム2〜3枚も作ればネタ切れも起こすし、また新たなアプローチを採用しても煮詰め切れずに世に出さざるを得ない、常に変化し続ける事によって既存ファンが離れる事による売上低下の危険性や、バンドとしての着地点やアイデンティティの喪失などのリスクがある事は想像に難くなく、普通のバンドよりも自家中毒に陥るスピードが圧倒的に早くなってしまった。この自家中毒の兆候がシーン全体で少し見え始めたのがこの1995年という年で、以降オルタナは失速していく事になる。

そんな風に混乱するオルタナシーンを横目に、ブッチ・ヴィグはサウンド・アティチュード双方における「オルタナティヴに対するオルタナティヴ」として、このGarbageというバンドを結成した。エレクトロサウンドに妖艶な女性ヴォーカルによるポップな楽曲は、ポップで何が悪い、商業的で何が悪い、自己模倣の何が悪い、自分達の確固たるスタイルを持っちゃいかんのか?、今やこんなバンド誰もやってないじゃないか、これこそ新たなオルタナティヴだろ? とでも言わんばかりのものであった。またこのスタイルは、シーンの混迷に今後数年先に巻き込まれる事を避ける為の予防策という側面もあったのだと思われる。
元々ブッチ・ヴィグは、スティーブ・アルビニと違ってコテコテのオルタナ主義者ではない。むしろどちらかと言うとポップ志向のプロデューサーである。前述の『Nevermind』や『Siamese Dream』も、オルタナティヴロックのアングラ性をなるべく損なわず、如何に大衆が受け止めやすいレベルまで昇華出来るか、というテーマの元プロデュースされている。後にJimmy Eat WorldやGreen Day、Foo Fightersなどを手掛けている辺りも、結局彼の目指している音楽が「商業性と非商業性の共存」という所であるからだ。それ故、Garbageがここまでポップに振ってきたという事実は、ブッチの理想像に忠実に接近していった結果であり、またGarbageが「オルタナティヴに対するオルタナティヴ」を体現し得たのもある意味必然とも言えた。
Garbageはデビュー時の音楽性を、以降多少マイナーチェンジしながらも基本的には変えず、その代わりに作品を出す毎にそのクオリティをよりブラッシュアップしていく方法論を取っている為、新規ファンにも既存ファンにも優しいバンドであり、レーベルとしても音楽性の変化が少ない分マーケティングも容易であった。90年代終盤で、世間が難解化していくオルタナに飽きてより分かりやすいニューメタルやポップパンクに走る中で、そういった層もちゃんと取りこぼさずに捕まえていった為、セールスも安定していた。
この「敢えて音楽性を変えない」スタイルにより、自分達のカラーはキープしつつ、より洗練させる事で、元々持っていた唯一無二の個性をより強烈なものへと変化させていき、その方法論の一つの到達点としての作品が、この4thアルバム『Bleed Like Me』である。
元々やってる事の基本は今までと何ら変わらないが、楽曲のキャッチーさ、及びサウンドの奥深さ双方においてより進化・深化を遂げ、リスナーにとってより飲み込みやすくなっている。それでいて初期のアクの強さは一切薄れていない。爽快なポップチューン「Run Baby Run」も、ダークなダンスナンバー「Metal Heart」なども、全てがクッキリなGarbage印。これまで聴いてきた人でも安心してとっ付き易い(逆に言えば新鮮味には多少欠けるけど)し、よりクッキリした音像と相まって元々あった中毒性も更に高まっている。
だが作品のクオリティの高さに対し、この頃バンド内は混乱していた。楽曲制作とその改良、リリースとツアーなどプロモーション、というサイクルを早い段階で作り上げたGarbageだったが、システムをずっと動かしっ放しでは当然ガタも来る。自転車だって定期的にオイル差してやんないとスムーズに漕げなくなってくるし。10年間休みなく、ブッチに至ってはプロデューサー業との二足の草鞋でやりながらもここまで続けてきたので、メンバーの疲弊も強まっていた。事実、本作のレコーディング中にシャーリー・マンソンが声帯を壊すという事件も発生している。コレをきっかけとしたのかしてないのか、元々疲れが溜まっていたメンバー間に徐々に緊張感が走るようになり、作業は遅々として進まなかった。何とか完成してリリースされるも、ツアーは一部日程がキャンセルされ、以降バンドは活動休止状態に突入する事となる。以降ベスト盤用にシングルを書き下ろしたりなど散発的な活動はあったが、本格的な活動再開は2012年まで待たなければならなかった。
【好きなアルバムについて語る】サカナクション - 834.194

2019年リリース、サカナクションの通算7枚目のオリジナルアルバム。読み方は「はちさんよん、いちきゅうよん」であるが、後にその数字から「ヤミヨイクヨ(=闇夜行くよ)」という呼ばれ方もされているとか。
前作『sakanaction』(2013)から約6年ぶりの新作となる。この間にも国民的ヒットシングルとなった「新宝島」のリリースや、これまでの総決算的ベストアルバム『魚図鑑』(2018)が発売されたなどはあったが、オリジナルアルバムのリリース間隔が6年にも及ぶというのは近年の日本のメジャーシーン、特に彼らクラスのバンドにしては非常に珍しい。大体が長くても2〜3年とかだもんなぁ。
サカナクションというバンド自体は知っていたけど、曲の方はリアルタイムでシングル「アルクアラウンド」のPVを見ていた程度にしか知らなかった。今思うと何故今更彼等の音楽をちゃんと聴こうと思ったのか、そのきっかけが思い出せないのだけれど、まぁ多分「新宝島」の影響だろうなぁ、あれめっちゃ良い曲だもん。
前述の通り、本作は6年のブランクを経てリリースされているが、その間もシングル・マキシシングルは絶え間なくリリースを続けており、更に2018年にはベストアルバム『魚図鑑』もリリースされている。また本作はこれまでのVictor Entertainmentから、傘下内に立ち上げた自主レーベル「NF Records」からの初のアルバムとなっており、内容としては前作以降のシングル(一部はベスト盤にも収録された)を一通り網羅した上で新曲を交えたものとなっており、前述の「新宝島」も収録されている。
ただ、6年間の間にシングルとして世に出た曲(カップリング含め)の多くが収録された結果、それらがアルバムの半分近くを占めてしまう状態であり、2枚組というボリュームにも関わらず「新譜なのに新譜感があんまない」という感想はちょっと抱いてしまう。ちなみにAmazonのレビューでの低評価コメントの内容は大体これ。まぁ気持ちは分かるよ、何となく。
元はと言えば、山口一郎氏(Vo.Gt)と岩寺基晴氏(Gt.)の2人が地元北海道で結成した「ダッチマン」というバンドが解体・再編成される過程で生まれたユニットとしてスタートしたのが、このサカナクションである。当時は山口氏がDJをし、岩寺氏がそれに合わせてギターを即興で弾く…という(悪い言い方をすればいかにも売れなさそうな)スタイルであったそうだ。だが両名ともテクノなどの電子音楽に造詣が深く、それがバンド形態になった際のバンドサウンドと電子音のバランス感覚に生かされている。その後デュオでのスタイルでは早々に限界を迎えたのか、地元のバンド仲間を集めて現在のメンバーでのバンド形態へ発展、その後地元の大型フェスへの出演を果たし、それをきっかけに一気にメジャーデビューへの階段を駆け上がっていった…というのが、すごく雑に纏めたバンドのスタートのお話。
ちょっとポストロック臭も匂わせる所謂「下北型邦ギターロック」に、テクノなどの電子音をチャラくなり過ぎない絶妙なバランス感覚で取り入れ、それにちょっと懐かしさも感じさせるメロディーラインを乗せ、インディー的密室感をギリギリ超えない範疇の中でより多くの大衆性を掴んでいく、というアプローチで現在のサカナクションのスタイルが形作られていった。後に邦ロックシーンで爆発的に流行する4つ打ちビートも、かなり流行初期段階で取り入れていたような気がする。オリジネイターが誰かは今や分からないけど、流行らせたのはまぁ間違いなく凛として時雨だろうな。
本作『834.194』リリース前後、山口氏は「作為的なものと、そうでないもの」という趣旨の言葉を様々な媒体で発言していた。噛み砕かずに言えば「売れ線か、そうでないか」という事で、要するに「周囲が求める"サカナクション像"」と、「自分がアーティストとして作りたい"サカナクション像"」という2つの狭間で揺れ動き、その両立を目指す、或いは折衷地点を探していたのだと思われる。恐らく前作『sakanaction』の時点で同様の悩みは既に抱えていたのではないかと推察する。クラブミュージックやミニマルミュージックからの影響をより多面に押し出した内容の同作は、従来のサカナクションのパブリックイメージに加え、「より自身のルーツや本来のコンセプトへ回帰して、純粋にやりたい事をやりたい(山口氏は「自身のルーツはライブハウスよりクラブである」といった発言も多い)」という志向を少しでも多く取り入れようという試みも感じられた。需要と供給の間で揺れ動くというのは恐らくどのバンドも直面する問題だとは思うが、彼等もまたそういった過去の例外に漏れず悩んでいたのだろうな、というのは『834.194』に収録されたシングルからも推察出来る。前作以降にリリースされ、本作『834.194』にも収録されたシングル群の楽曲は、今まとめて聴いてみると、自身のルーツでもあるアンダーグラウンド志向と、これまでの作品群で出来上がったパブリックイメージの間を広い揺れ幅で動いている。
ただこの、所謂売れ線タイアップ曲と純粋にやりたいように作った楽曲を半々に混在させて完成したアルバム『sakanaction』、バンド史上初のオリコン1位、売上枚数20万枚、更にツアーの総動員8万人超えと、要するにバカ売れしてしまう。更にはその年の紅白歌合戦にも出場決定と、「人気バンド」から「国民的バンド」へのランクアップを一気に果たしてしまう。予想外の展開である。まぁ売れる事は確かに良い事なんだけど、元々は今までいたファンに「僕達こういう一面もあるんですよ」っていうのをプレゼンしたかっただけなのに、結果より多くの新規ファンまで獲得、より高い注目も浴びるようになってしまう。
「いやいやいやいやちょっと待ってこれはマズいよ、いやマズいわけじゃ無いんだけどさ、売れるのは嬉しいんだけどさ、ただほら、その…」
みたいな事をメンバーが言ったかどうかは知らないけれど、それに近い心境だったんじゃないかと思われる。
売上や注目度の急激な上昇は必ずしもアーティストに良い影響を及ぼすとは限らない、というのは歴史が証明しており、極端な話過去に多くの犠牲者を生み出す要因となっている。マスからの注目やレーベルからの期待の増加に比例して、プレッシャーも大きくなっていく。そうするとみんな余裕が無くなってきて、何気ない瞬間でもなんかピリピリしてくる。今まで何とも思わなかった楽屋の沈黙がやけに重い…後に山口氏も発言しているが、紅白の頃になるとバンド内の空気は非常に悪いものになっていたという。段々と曲作り作業にも悪影響を及ぼしかねない所まで行き、この状況に危機感を覚えたサカナクションは、やっと掴んだ成功を全て手放す覚悟で、レーベルからの反対も押し切って非常に内政的なシングル「グッドバイ / ユリイカ」を世に出す。ミドル・スローテンポで、尚且つ今まで以上に密室感の強いダークな質感の同2曲は、これまでのサカナクションのイメージ及び「シングルリリースに耐えうる(=売れる)曲」という範疇からも大幅に逸脱していた。かつてNirvanaが『In Utero』(1993)で、またRadioheadが『Kid A』(2000)でやろうとした事(「商業的自殺」ともいう)を、サカナクションはこのシングル1枚でやろうとしたのだった。彼等はこのリリースを「マスからのドロップアウト」と称していたが、それは自分達自身を、そして自分達のアイデンティティを守る為の、必要な選択だった。
その後も内外共に混迷を極めていたバンドは、当時映画『バクマン。』の劇伴と主題歌の制作が思ったより進まない事や、草刈愛美氏(Ba.)の妊娠出産なども重なった事から、ライブ活動を休止することになる。その後バンドは前述の「マスからのドロップアウト」というコンセプトに加え「マジョリティの中のマイノリティ」という立ち位置の確立の為に動くことになる。これについてインタビューなどで度々語られてはいるが、要するに「純粋にやりたい事をやれる土壌を作る」という事である。ライブを休止する事で一歩後ろに下がり、リラックスする事に成功したのか、その後の活動はよりノビノビと、かつ柔軟に行われていく。自らの理想郷を作り上げるべく、カルチャー複合型イベント「NF」を自主開催、更に自主レーベル「NF Records」の設立など、サカナクションはよりクリエイティヴな方向へ向かってアクティヴに進んでいく。そしてNF Records第一弾リリースとして、映画『バクマン。』主題歌「新宝島」を発表。これがブレイクスルーとなり、またこの曲で、「マジョリティの中のマイノリティ」という立ち位置をより明確化する事にも成功する。その後ベスト盤リリースを挟みつつ、既に手広く展開していたNFなどの様々な活動により説得力を持たせる為にも、改めてニューアルバムの制作に着手、マイペースにコツコツとアルバム制作は進み、発売延期が一度あったものの2019年6月19日にようやくニューアルバム『834.194』が世に出たのであった。

タイトルの『834.194』という数字の意味は、サカナクションが北海道で活動していた時に利用していた「スタジオ・ビーポップ」と、現在利用している東京の「青葉台スタジオ」の直線距離(834.194km)が由来で、地元札幌と現在いる東京の物理的距離と、サカナクションを始めた時と現在の音楽的な景色の変化を例えている。
大まかに言うと、親しみやすい"サカナクションらしい"楽曲をDisc1に、より実験的・内省的な楽曲をDisc2に配置している。両ディスクの最後には、ダッチマン時代に作られた「セプテンバー」という楽曲が、アレンジ違いでそれぞれ収録されている。
キャッチーなシングル曲を中心に1曲1曲が際立ったDisc1と、内省的なカラーの曲達がお互い溶け合うような絶妙なコラージュを描くDisc2といった具合に、ハッキリとコントラストが分かれている。この方法はベスト盤『魚図鑑』でも実践されていたもの。2枚分を連続で通して聴くと、明るい前半からまるで斜陽の如く暗くなっていき、最後に再び夜明けが訪れるようなグラデーションを描いているのが分かる。
その夜明けの先にあったのは、自らの原点、音楽を始めた時の初期衝動であり、「セプテンバー -札幌 version-」の荒削りなアレンジが、そのメタファーとして表現されている。
…とは言うものの、Disc1、2共に新曲群なども含めて、音楽的に従来と何かが大きく変わったのか、と言われれば、ぶっちゃけそこまででもない。けれども「歌」や「言葉」への重きが前作とは違って聴こえる瞬間が多い。「忘れられないの」「マッチとピーナッツ」などで見せたシティポップへの目配せも、元来サカナクションのメロディラインの持つ「昭和歌謡っぽいちょっと懐かしい感じ」によりフォーカスを当てた結果出てきたものだと思われる。これについては、「グッドバイ」をリリースした時に山口氏が「純粋に歌を聴いて欲しかった」と語っており、こういったマインドの変化も後の曲作りに反映されているのではないかと推測。
まぁでも、結局のところ色々考えると、「グッドバイ」以降の山口氏の抱えていた悩みって、すごく雑に言うと「ちょっと考え過ぎた」だけだったのかもしれない。結果的にセールスは波があったとは言え及第点は余裕でクリアしてるし、現在では従来のサカナクションのフォーマットから外れた楽曲でもマスに訴えかける力は全く失われていないし、ファンも付いてきてくれている。今作の売上も、前作は上回れないながらも現時点で10万枚は超えている(最も、サブスクが前と今では普及度が全然違うので、正直CDの売上枚数ってアテにならない感はあるけれど)。ただ「好きな事やってもみんな付いてきてくれる」という手応えが欲しかった、それ故の活動の多角化だったんだろうし、その手応えが得られたっていう確信が本作制作時のメンバーの精神面にかなりポジティブな影響を与えているのは間違いないと思う。
最終的に1周回って戻ってきた感は若干あるが、マインド面では全然違う状態で作られる、よりフレッシュなサカナクションらしいアルバムとなった。
「色々ありまして、今これだけの事が出来ます」っていう暫定座標記録と、「これからとにかく好きな事ガンガンやっていきます」という今後への決意表明という2つの側面を持った作品が、この『834.194』である、っていうのが、このアルバムに対する自分の今の結論である。
【好きなアルバムについて語る】Enter Shikari - Nothing is True & Everything is Possible

2020年リリース、英国発"レイヴコア"バンド、Enter Shikariの通算6枚目のアルバム。
新型コロナウイルスの世界的流行の真っ只中である4月にリリースされた。当然ながらツアーなど出来るはずもなく、2020年10月現在、本作の収録曲は未だライブで演奏はされていない。
前作『The Spark』(2017)からおよそ2年半ぶり。2019年にリリースされたシングル「Stop The Clocks」は収録されていない。前作ではレトロフューチャーなデザインのコンピュータの様なマシンがアイコンとして使われていた(ステージで実際にシンセサイザーとして演奏に使われている)が、本作ではアイコンとしてジャケットにも採用されているミケランジェロ風(?)な石像が使われている。これどっかで見た事あんだけど何だっけ?思い出せそうで思い出せない。あぁ歯痒い…。
2000年代中盤以降のイギリスやアメリカのアンダーグラウンドでは、従来のスクリーモをよりヘヴィに、メタリックかつシャープに発展させた音楽が、ポスト・ハードコア或いはメタルコアという呼称で市民権を得つつあった。そこにレイヴまたはクラブミュージック由来のエレクトロサウンドを半ば強引にぶち込み、"レイヴコア"と名乗り、同ジャンルの英国での第一人者として2007年に1stアルバム『Take To The Skies』で鮮烈なデビューを飾ったのがEnter Shikariだった。ちなみにその翌年である2008年、大西洋を挟んでアメリカではAttack Attack!がクラブミュージックとメタルコアを融合し『Someday Came Suddenly』を引っ提げデビュー、同ジャンルの第一人者としてシーンを作っていく事になる。
Enter ShikariもAttack Attack!も、そのちょっと後に出てきたWoe, Is Meとかもそうだったけど、元はMySpaceなどに上げた音源が大衆或いは大手レーベルの目に止まってデビューしていったのだが、この経緯、色んな意味で時代を感じる。今思えば本当に一瞬だったけど「ホットなバンドを見つけたければMySpaceをディグれ」みたいな風潮があったのだ。今じゃ誰も見ちゃいないけどね。
彼等の登場によって、同じようにエレクトロサウンドと融合を果たしたメタルコアバンドが英米だけでなく様々な国から登場してシーンに大量に溢れかえり、その勢いのまま、手始めに当時ポップパンクや初期スクリーモの祭典だったWarped TourとDownload Festivalを徐々に侵食、新しいもの好きのキッズを片っ端から取り込み、インターネットの拡散力も借りて世界規模に名前を轟かせていく。
ちなみにこの流行は日本にもすぐ波及し、Fear, and Loathing in Las VegasやCrossfaithなどが"ピコリーモ"などと呼ばれ注目を浴びるようになり、激ロックなどのメディアがインフルエンサーとなり日本のライブハウスシーンにも多量のフォロワーを生んだ。
メタル又はポストハードコアに電子音を合わせるというアイデア自体は既にあったけど、どれもシンフォニックかゴシック、或いはインダストリアルなものといった、硬派な志向であるものが殆どであった。そんな中でクラブシーンやレイヴカルチャー由来のダンサブルなエレクトロを導入した彼等の登場は、今まで頭振ってモッシュする為のメタルに「飛び跳ねる」「踊る」と言った要素が初めて入ってきた瞬間でもあった。そこには従来のメタルにあった悪魔崇拝やら宗教観などの小難しい世界観は一切無く「とりあえず何も考えなくて良いから暴れて踊っとけ」という分かり易さ(正直頭の悪そうな感は否めなかったが)もあって、新しいもの好きのキッズにはバカ受けした。ただその一方で、従来メタルの(ある種の取っ付き辛さから来たものだろうけど)孤高性なども一切無かった為、コアな(保守的な)メタルファンからはかなり冷ややかな目で見られていたとは思われる。分かんないこれも俺の周りが当時そうだっただけだけど。逆にメタルはDragonForceかArch Enemyくらいしか知りません程度の人にはすごくウケてた。

しかし、流行るスピードが速いと飽きられるスピードも速くなる。ましてやメタルコアもクラブ・レイヴミュージックもそこまで拡張性が広い音楽ジャンルではなかった為、多くのバンドが拡大再生産のループから抜け出せずマンネリ化、キッズからも次第に飽きられていく。確かにこの手の音楽は流行り始めから泡沫ジャンルだっていう陰口はずっと言われ続けていたけど、だって正直この手のバンドって、ザクザクズンズンしたブレイクダウンにデスボイス、サビはクリーンメロディにチャラい電子音ってお決まりのパターンで結局それだけなんだもん。中にはSkrillexの影響でダブステップを取り入れて新機軸と銘打ったバンドもいたにはいたが結局そこまでで、音楽的行き詰まり或いは創造性の不一致からそのまま解散、良くて空中分解、或いは誰にも知られずにフェードアウトしていくバンドも少なくなかった(そう考えるとEskimo Callboyってすげぇな。一生あのまんまだもんな)。かつてオリジナイターとして散々持てはやされたAttack Attack!も、相次ぐメンバー脱退の後に2014年にひっそりと解散という、何とも虚しい最期を迎えている。当時出てきて現在も生き残っているバンドの多くは、最終的にチャラいエレクトロを捨てて、より硬派なモダンハードコア色を強めていくか、他ジャンルとの折衷地点を求めるなどして、シーンの変化に適応していった。
一方シカリはというと、同じように泡沫バンドかと誰もが言う中、そんなメタルコアシーンなどほぼ完全知らんぷりな方向へ進んでいく。元々純粋なヘヴィさでもチャラさでもアメリカ勢には負けていた(1st『Take To The Skies』もやってる事の基本は間違いなくメタルコアだけど、プロダクションの影響かアメリカ勢より軽く聴こえる)ので、ここで勝負しても勝てないと早い段階で判断したのか、バンドサウンド面では逆にインディー・ローファイ的なハードコア・パンクスタイルへ接近、エレクトロ面では分かりやすいピコピコ感を抑えてよりアンダーグラウンドなレイヴ感を強めていく。また更にラップやスポークンワード、ドラムンベースなどの新たな音楽的要素を片っ端から取り込む貪欲性を武器に、アメリカ勢には無い実験性と、インディーロック的密室感も取り入れた独自の路線へと進んでいった。
そしてイギリス・アメリカ共にエレクトロニコアムーブメントがほぼ終結した2015年に発表したアルバム『The Mindsweep』で、これまで突き詰めてきたシカリ型エレクトロニコアの完成形として帰結。どこかサークル的ノリだった密室型ポストハードコアからの脱却、SF的壮大さを持ったサウンドスケープと疾走感溢れる曲調、プログレッシブな曲構成などで、他のエレクトロニコアバンドとの格の違いを見せつけると同時に、ロックシーンでも唯一無二の個性を持ったバンドとして、不動の地位を確立する事となった(個人的にもこのアルバムはシカリの最高傑作だと思っている)。ちなみにBring Me The Horizonが名作『That's The Spirit』を出したのも2015年。更にWhile She Sleepsの『Brainwashed』、Young Gunsの『Ones And Zeroes』や、あとDon Brocoの『Automatic』もこの年かぁ。個人的に2015年ポストハードコアシーンは結構豊作だったな、今思えば。
だが、『The Mindsweep』で1つの到達点に辿り着いたシカリ、独自路線探究の旅はまだまだ終わらなかった。翌2016年にThe Mindsweepの方法論に、よりシンプルなポップさを加えて作られたシングル「Redshift」で手応えを掴んだ彼等は、デビュー10周年となる2017年にリリースした『The Spark』で、レイヴ色・ポストハードコア色共々一気に薄め、『The Mindsweep』でも一部取り入れていたデジタル・アンビエント、シューゲイザー的空間演出をより強調、今まで以上に親しみやすいメロディと歌を全面に押し出した、非常にポップな1枚として仕上げてきたのだ。まるで「2000年代半ばくらいのColdplayを完全デジタルで再現してみました」と言わんばかりの空気感を持ったサウンドに当初は非常に驚かされた記憶がある。
アグレッレションもエグみも捨てた、新たな境地を求めて制作された『The Spark』は、従来からあまりにガラッと変わった音楽性にも関わらず評論家・ファンからも非常に好評で、今後のEnter Shikariの音楽によりタイムレスかつ、より多くの層への訴求力を抱かせるきっかけとなった。乱痴気なレイヴサウンドや激しいスクリームなどの飛び道具に頼らなくても、美しいメロディラインと自分たちなりに追求したポップさだけで十分以上に勝負出来る、そして今後10年20年経過しても劣化しない音楽を"Enter Shikari"として作る事が出来るという手応えは、バンドにより自信を与えていく。特にルー・レイノルズ(Vo.)は、それまで自分の声を1つの楽器のように捉え、変幻自在にスクリームやラップ、スポークンワードなどをメインに出していた歌唱法から、「歌を歌としてしっかり歌い上げる」スタイルへとシフトした事で、今までありそうで無かった「王道なボーカリスト」としての一面を出す事にも成功した。若気の至り全開の、いかにも頭の悪そうなガキンチョ4人衆だったEnter Shikariは、エレクトロニコアのオリジネイターとしてだけでなく、気付けばイギリスを代表するビッグネームとしてシーンに君臨する存在となったのだった。

さてさて、そんな歴史を歩んできたシカリの2020年の最新作『Nothing Is True & Everything Is Possible』だが、良い意味で前2作と比べても荒削りな作品である。
『The Mindsweep』『The Spark』両方とも明確なコンセプトがあって、それを忠実に再現すべく細部までしっかり拘った作りだったが、本作は敢えてコンセプトやトータルの完成度よりも(勿論大事にはしてるんだけど)、より衝動性を重視した、言わば「今の俺達が作る『Take To The Skies』ってどんな感じなのかな?」というテーマで制作されたような質感である。『The Spark』で掴んだメロディを生かす為の空間演出的アレンジと、『The Mindsweep』以前のアグレッションやダークな雰囲気の双方を、やや歪なバランスながら上手く楽曲中に落とし込み、よりサイバティックな音像を作り上げている。
またインタールード的楽曲を多く用いる事でアルバム全体をシームレスに繋げ、同時により多彩なカラーを与えている。この辺りはThe 1975辺りからのインスパイアもあるのだろうか、なんて想像してみたり。アルバム全体を見渡すと前作での洗練された感は無いが、「この先何十年も残る"Enter Shikariの音楽"とはどのようなものか?」という彼等の飽くなき音楽的探究の旅が、ここでまた新たなフェイズに移行した事を表現するアルバムとなった。前身バンド結成から21年、現体制になって17年という実はすごくキャリアも長く、音楽性もどんどん変わっていく彼等(ファッションのセンスだけは相変わらずである)だけど、"Enter Shikari"という名前に込めた意味…「外へ飛び出し、自らの手で望む物を手に入れろ」、それは未だブレていない。

3rd『A Flash Flood Of Colour』(2012)辺りから、なんとなく目つきが変わってきたなぁという印象はあったのだけれど、作品を追う毎にその目つきが鋭くなってきている感あるEnter Shikari。本作もその鋭い目つきで我々に何かを訴え続けている。
デビュー当初は頭の悪いハナタレ小僧が悪ノリ的に作った音楽がたまたまバズってしまった、みたいな感じのバンドだったけど、作品を追う毎にその音に知性を感じさせるようになっており、ある瞬間からこの世の全てを悟ったかのような顔つきで聴き手に迫るような音楽を作るようになった。不気味なんだけど妙に説得力あって、ずっと聴き入っちゃって、最終的には気付いたらカルトの一員になってしまっているかのような、そんな不思議な引力も持ち合わせるまでに至った。原色を多用した、まるでフリー素材を切り貼りしただけのような、一見するとダサい本作のジャケットも、音を聴いた後は非常に複雑なアートに見えてしまうから不思議なものである。
【好きなアルバムについて語る】The Beatles - The Beatles (White Album)

1968年リリース、The Beatles通算10作目のフルアルバム。
真っ白なジャケットにエンボス加工でバンド名が書かれただけの、もはやシンプルとかを通り越して何の意図も無いアルバムジャケット、ジャケットだけでなくサウンド面でも前作までのサイケデリック色が完全消失した事や、バンド史上初(結果的にフルアルバムとしては唯一。ちなみにマジカル・ミステリー・ツアーの一番最初のイギリス盤のやつは2枚組EPだったりするけど。あ、コレ余談ね)の2枚組アルバムという点も、今作が彼等のディスコグラフィに於いて特徴的な所以だったりする。一応正式タイトルは『The Beatles』って立派なセルフタイトル作なんだけど、「ホワイトアルバム」っていう通称が浸透し過ぎてて、もはや正式タイトルで呼んでる人など誰もいない。
68年って一応サイケデリック全盛の時代だし、ビートルズとしてもコレの1年前にあの『Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band』(1967)という、ジャケットから中身までコテコテにサイケなアルバム出していたし、何ならこれ作るちょっと前もサイケなノリの映画『Magical Mystery Tour』(1967)を作ったりとかしてたのに、たった1年でのこの突然の心変わりは一体。以下に記すが色々思い当たる理由はあるが、結局のところ真意は未だに謎である。
個人的な話だが、「多彩な方向性の楽曲が多数揃ってて捨て曲も特に無いけど、全体としては纏まりに欠けるアルバム」の事をよく「ホワイトアルバム的な」って言ったりしてる。個人的にだけど。例えばTodd Rundgrenの『Something Anything?』(1972)とか。
1965年頃、それこそアルバム『Rubber Soul』を作った辺りから、ビートルズは初期の「分かりやすいラブソングをポップに鳴らすアイドルバンド」的立ち位置からの脱却を試み始める。それと同時にこの辺りから、ジョン、ポール、ジョージ、リンゴそれぞれの音楽的・人間的個性というのも少しずつ際立ち始め、「あくまでポップスに拘るポール、より内省的な世界観を描くジョン、皮肉屋のジョージ、平和の象徴リンゴ」というようなキャラが少しずつ形作られていった。
この様な脱アイドル化とアート面の更なる深化を志向したのは、プライベートでのドラッグ体験やボブ・ディランからのインスパイア(これは特にジョンに関してだけど)などもあっただろうけど、結局のところはルーティンワークと化したツアー活動への嫌気から。だって当時の音響設備では5万人の女の子の熱狂に勝てる音量なんか出せるわけもなく、更にモニターなんて便利なものなんてもっと無いわけで、結果何が起こったかと言うと、ステージに立って演奏してても、全てファンの泣き叫び声に掻き消され自分達の音なんか殆ど聞こえないような状態になってしまうという、現代ではにわかに信じがたい環境下に置かれていたという。最初こそちゃんとリハーサルもして、そんな過酷な状況下でも必死にアイコンタクトして縦もしっかり揃えて、各々ミスもしない、ハモりも外さないというクオリティの演奏が出来ていたけど、そんな見事な演奏も客席の連中はキャーキャー叫んでるか、ステージに向かって突撃しては警備員に捕まっているか、中には叫び過ぎて失神してる奴とか、まぁ要するに誰も聴いていないワケで。そんな中ではせっかく作った新曲もセトリに入れる気も失せるし、中音も外音もろくに聴こえない環境で演奏したってスキルアップや新たなノウハウを掴むなど出来る筈もないワケで。…ってそんなツアー活動を結局デビューから4年間も続けたんだから、彼等の忍耐強さって相当だったんだと思う。
ツアーではそんな一方で、スタジオ内では4トラックレコーダーを2台同期させる事に成功。よりレコーディングで出来る事が広がっていく。今まで一発録りの流れ作業だったレコーディングが、リテイクが容易になった事、オーバーダビングで録れる音の種類も質も一気に上がった事で、より細部に拘った作業が可能になった。この頃辺りから「未発表テイク」の量が増え始めていき、これらは多くが後に海賊盤として世に出回る事になる。8トラックでのレコーディングという過去最高に優れた環境を手に入れた事によって、バンドの拘りや好奇心はどんどんエスカレート、リテイクの繰り返しだけでは飽き足らず、「こんな楽器使ってみようぜ」「こんな音入れてみない?」「ちょっと複雑なハモリとかやってみよう」「てかこの曲ギターいる?」「なんか逆再生してみたらめっちゃサイケ!やば!」などと、当時としては前代未聞のアイデアが湧き水の如く溢れ出ていき、遂にはツインギター4ピースバンドが生演奏で再現出来る限界をあっという間に飛び超え、1965年に『Rubber Soul』、1966年の『Revolver』という作品を生み出してしまう。ジョージはインド文化へ傾倒する勢いそのままにシタールやタブラを取り出し、ジョンはテープの逆再生を利用したギターソロを採用、ポールは弦楽四重奏の曲を作ったりするなど、もはややりたい放題(多分このテンションの上がり方はLSDの影響もあったのかなぁ)。従来通り通常営業だったのはリンゴだけだった。
「これ以上音を重ねたらライブはどうするんだ!?」
…メンバー内、或いは外部の人間から絶対こんな意見が出ていたに違いない。かのブライアン・エプスタインもきっとそう思っていたに違いないが、「でもあの聴衆を見てみろよ、誰も俺達の演奏なんかまともに聴いてないじゃないか」とメンバーに反論されては、返す言葉も無かった。それに若手時代からまるで親のように彼等を見守ってきたエプスタインとしても、疲弊しきっているツアー時とは別人のようにイキイキしている4人を見ているのもそれはそれで楽しい…って具合にちょっとモヤッとはしていたんじゃないかなぁ。一方プロデューサーのジョージ・マーティンは、ライブなんて自身の管轄外だから全く関係ないので、「良いぞもっとやれ」と積極的にバンドのスタジオワークを後押ししていたんだろうな、多分。てか絶対そう。だって「ダライ・ラマが山頂で説法してる風な声が出したいんだけど」っていうジョンの意味不明な無茶振りに対して「じゃあレズリースピーカー通せばええんちゃう?」って返しどうやったら思いつくんだよって話。
そして1966年の日本武道館でのライブで、初めて静かな聴衆を前に演奏したことで、自分達の演奏力の低下を痛感、その後のフィリピンツアーでもゴタゴタや、そしてかの有名なジョンの「キリスト発言」がアメリカで大炎上した事へのフラストレーションなどもあって、兼ねてから抱いていたツアーへの不満が限界に達したビートルズは、同年のキャンドルスティックパーク公演(アメリカ)を最後に、遂に人前で演奏する事をやめる。
その後「これからはターンテーブルが俺達のステージだ」と言わんばかりに、バンドは曲作りとレコーディングに打ち込んでいく。LSDやマリファナにも後押しされた格好で、彼等のインスピレーションは止まる事を知らず、1967年リリースの、世界初のコンセプトアルバム『Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band』で1つの頂点を迎える。スウィートなラブソングを奏でるマッシュルームカットのアイドルバンドとして現れたビートルズは、たった数年のうちに、無精髭に丸メガネ、ボサボサ髪の一流アーティスト集団へと変貌を遂げたのだった。
ところがその暫く後、マネージャーのブライアン・エプスタインが急死(真相は半世紀以上経った今でも謎に包まれている)。リバプール出身の4人の田舎者を世界的スターにのし上げた仕掛人としてだけでなく、メンバーの精神的支柱でもあったエプスタインの死は彼等に大きなショックを与える。『Sgt. Pepper's〜』の成功から来る達成感か、メンバーそれぞれがソロワーク(ジョージはソロアルバムを作り、ポールは映画音楽を手掛け、リンゴは俳優業を始め、ジョンはヨーコと出逢う)に手をつけ始めていたりしていた中での緊急事態だった為、メンバーの結束が緩む事を危惧したポールが主導となって完全自主制作映画『Magical Mystery Tour』を企画・制作するも大ゴケ。ツアーを辞めてやっと自由な時間を手にしたばかりのタイミングで訪れた突然の悲劇と、その後立ち直りを目指した企画の失敗などで、バンドは内外ともに混乱していく。一度頭の中を全てフラットに戻す為、そして同時に彼等を蝕んでいたLSDなどのサイケデリック・ドラッグからのデトックスも目指し、バンドはマハリシ・マヘシ・ヨギの元で瞑想修行をする為インドへ渡る。まぁここでも結局何やら色々あったらしいけど、結果的には心身共にスッキリした上でイギリスへ戻り、インドで修行の合間にメンバー各々が作った楽曲群を一気にレコーディングして出来上がったのが、今回ご紹介する『The Beatles』、通称ホワイトアルバムである。うわっ前フリ長っ。

さて、インドでの瞑想修行の末、各々ある程度はスッキリして、また修行の合間で息抜き的に作った曲も手土産に、ビートルズはイギリスへ帰ってくる。
この時メンバー全員分合わせて既に40曲以上が出来上がっており、スタジオ前に一旦ジョージの家でこれらを整理、最終的に26曲に絞られた上でデモテープが制作された。この時のデモテープは後に「イーシャー・デモ」と呼ばれ、海賊盤やアンソロジー、記念リイシュー盤ボートラなどで世に出ている。
この26曲を引っ提げてスタジオ入りし、後にまた更に新曲を加えたりして最終的に30曲以上が完パケする。多くはやはり瞑想の成果か、これまでのサイケ色は完全に消え去り、よりシンプルかつオーガニックな、バンドサウンド中心のサウンドに変化した。過度なオーバーダビングやエフェクトなども殆ど登場しない。中には「Revolution 9」のような前衛音楽など実験的な曲もあるものの、概ね非常に風通しの良い、スッキリしたサウンドでアルバムカラーは統一されている。こうして結果的に「脱サイケ」化した理由としては、前述の瞑想により心身共にデトックスした結果か、或いはインドに赴いた際に手元にあったのがアコギしか無く(あ、でもピアノくらいはあったのかなぁ)、自宅ならすぐ近くにスタジオがあったけどマハリシの施設の近くにそんなもの無いし…という状況も無関係では無かったと思われる。
みんないっぱい曲作ったし、いっぱいレコーディングしたなぁ、しかもどれも良い曲ばっかだし…
…とここで気付く。「あれ、曲多くね?」
ジョージ・マーティンも一言「うん、曲多過ぎるよ。1枚分に削らないと」
じゃあここからどう絞って纏めていこう…となったところで、どういうわけか意見が全く纏まらない。
それもそのはず、40曲作ったと言っても、殆どの曲はメンバーそれぞれ1人の作業で完結しており、作曲:レノン=マッカートニーとクレジットされた曲も、実際は共作など殆どしていなかった。2人が共作しなくなったのは別にかなり前からだけど、この頃になるとそれぞれの個性やエゴが際立ち過ぎて、もはや共作しようにも相容れなくなってしまっていた。ジョージもジョージで、軸は定まらないし数も少ないものの今まで以上に型から抜け出した曲を多く出していたし、リンゴもマイペースにコツコツ作っていた「Don't Pass Me By」を初の自作曲としてアルバムに提供し、相変わらず控えめながらもようやくバンド内で明確な自己主張をし始めていた。
ジョージはアンソロジーでのインタビューで、「当時のビートルズは多くのエゴが渦巻いていて、曲を削るに削れなかった」といった趣旨の発言をしている。結局レコーディングも、蓋を開けてみればメンバー全員が参加した曲は意外と少ない。スタジオに籠りっきりで多重録音に熟れ過ぎていたし、おまけにいよいよ本格的な8トラックレコーダーが導入されたりした結果、もはや自分で演奏出来る部分は自分でやっちゃうよね、という結論に至ってしまっていたのだ。誰かに弾いてもらうにしても「ここ後でソロ入れといて〜譜面に起こしてあるから〜」程度のディスカッションしかしなくなっていく(そんな事やってっから当時リンゴが一時的にバンド離脱しちゃったりしてね)。
それに、そもそも各自の曲作りの段階でアルバム制作までは想定しておらず、ただ気晴らしにギター爪弾きフフンと鼻歌で作った曲達に統一性などある筈も無かった。
だから「この曲は外していいんじゃない?」なんて軽はずみにでも言った際には、その曲を作った人間から猛反発を食らうか、「じゃあお前のその曲も外せよ!」みたいな喧嘩に発展しかねない空気に。ああでもない、こうでもない…4人全員がお互い譲らず、ジョージ・マーティンも交えて話し合う中、最終的には「もう全部入れちゃわない?2枚組とかにしちゃってさ」と誰かが言ったのか、LP2枚組、全30曲収録という、とんでもないボリュームで本作は世に放たれたのであった。
真っ白なジャケットにサイケ色の一切ないシンプルなサウンドは、当時フラワームーブメント真っ只中だった時代に於いては殊更特徴的で、まるで全員酔っ払った大宴会の席で1人だけシラフでいるようなものだった。
多彩過ぎるが故に統一性に欠けると評される楽曲群も、だからこそジャケットを真っ白にしてセルフタイトルを冠したと考えれば、「特にテーマもコンセプトも無いアルバムです。これが今の"ザ・ビートルズ"です。」という「テーマ」で纏まっていると捉えられる。
解散後のそれぞれの路線への布石と見る事も出来るし、即ちこの時誰も気付かないうちに既にビートルズは解散へと向かっていた、とする意見もある。
この頃のビートルズはApple Corps立ち上げなど新しい取り組みも幾つか始めていたが、肝心のメンバーが見てる方向全員バラバラではいかん、と危機感を募らせたポールは、再びバンドを団結させる為に、原点回帰的なライブ一発録りアルバム『Get Back』を企画する。だが時既に遅かったのかタイミングが悪かったのか、後にこの「ゲット・バック・セッション」は悪夢として語り継がれる程メンバー間の関係を悪化させ、アルバムは一旦お蔵入りになる(後にフィル・スペクターの手により『Let It Be』として完成)。修復不可能な程に亀裂の入ったビートルズは、その後「解散」を視野に入れた上で『Abbey Road』(1969)へと着手していくのであった。
余談だが、ビートルズが解散した1970年、ジミ・ヘンドリックスやジャニス・ジョプリンなど当時のシーンを牽引していたアーティスト達が続々とこの世を去り、その前年にはローリング・ストーンズの「オルタモントの悲劇」など、様々な不幸によってフラワームーブメントは急速的に萎んでいく事となる。世間より一足早くサイケ文化から抜け出したビートルズが、あくまで結果論ではあるが、自身の解散を以てフラワームーブメント及び「1960年代」という時代の幕引きの一役を担った、という風に捉えるのは考え過ぎだろうか。
【好きなアルバムについて語る】Red Hot Chili Peppers - One Hot Minute

高校時代の記憶の半分くらいはレッチリ聴いてた自分。このアルバムも一時期全曲脳内再生出来る位には聴き込んだ。
何かと言われる1枚だけど、この前久々に聴いて、そろそろこのアルバムについてちゃんと考えてみるのも良いかもしれないなぁと思い立った次第。
1995年リリース、Red Hot Chili Peppersの通算6枚目のアルバム。
前作『Blood Sugar Sex Magik』(1991)までは2年おきに必ずアルバムを出していたのだけれど、今作はいつもの倍の4年ものブランクを経てのリリースとなっている。
制作前の1992年に、前2作を支えたギタリストのジョン・フルシアンテがワールドツアーの真っ最中に突然の脱退(後に復帰)、色んなギタリストを取っ替え引っ換えしながらやっとこさ残りのツアー日程を乗り切る中で、正式な後任ギタリストとして旧知の仲であり、地元カリフォルニアの先輩バンドでもあったJane's Addictionの元ギタリスト、デイヴ・ナヴァロに白羽の矢が立つ。
当時のレッチリはBlood Sugar〜の大ヒットにより、オルタナシーンを飛び越えて当時のアメリカを代表する超売れっ子バンドへと変貌している一方、ナヴァロの方は1991年のJane's Addiction解散後に組んだ新バンドDeconstructionがアルバム1枚で呆気なく解散したりと、ジェーンズ以降の具体的な活動方針が見出せない時期を過ごしていた。その為、バンドの高い注目度に耐えうる経験やある程度のネームバリューを持ったギタリストを欲したレッチリサイドと、同じく高いネームバリューのある環境での新活動を望んだナヴァロサイドとの思惑が合致した故の加入、みたいな感じだったんじゃないかと推察してみる。片や飛ぶ鳥を落とす勢いのバンド、片やロラパルーザを創設しオルタナシーンを牽引した伝説的バンドのギタリスト、となれば対外へのアピールというかプロモーションというか、話題性もバッチリ。レッチリとしてもせっかく掴んだ全米での成功をフルシアンテの身勝手な脱退(殆どバックれに近かったらしい)で失うワケにはいかないっていう危機感もあっただろうし、旧知のナヴァロなら自分達のノリも掴んでくれるだろう…っていう期待感とか、まぁ色々あったんでしょう。
まぁそんなこんなで、デビュー以来初めて4年ものリリースのブランクが空いてしまったと。
ナヴァロの正式な加入は1993年だけれど、それまでも多くのギタリストを急場凌ぎで加入させては捨て、加入させては捨て…を繰り返しながらライブは1度も飛ばさずにこなして来たお陰もあってか、世間の注目度が下がる事も無く、加入後に出演したWoodstock '94での電球パフォーマンスのインパクトもあって、新体制レッチリへの関心はより高まっていた。
そんな中で制作された通算6作目『One Hot Minute』。
前作『Blood Sugar Sex Magik』で確立した、間を活かしたグルーヴ感や泥臭さを前面に出したサウンドメイキング(レッチリ節として後々も続いていくスタイルの基本形とも言える)は、ナヴァロの持ち込んだエッセンスにより大きく影を潜めた。
ギターの音がフェンダー系からPRSとかそっち系に変わった点と、Jane's Addiction時代からのナヴァロの持ち味であるヘヴィながらもコシの効いたプレイによりサウンドは激変。そんなナヴァロに触発されたフリーとチャドのリズム隊も負けじと弾きまくり叩きまくった結果、前作で志向したグルーヴィーなファンクネスはほぼ消え失せ、逆にとにかく音を鳴らしまくって隙間を埋め尽くすようなハードロック的スタイルに変化した。
前作までのレッチリが上裸で跳ね回りながら野外で演奏してるような雰囲気だったのに対し、今作では何やら悪趣味な服装にメイクアップで、薄暗い地下のライブハウスで爆音出してるイメージ。まさにM-1「Warped」のPVまんまなんだけど。


曲作りのアプローチについては、ギター又はベースのリフを基にジャムって広げる…という方法はレッチリもジェーンズも基本的には同じだったので、フリーに負けじとナヴァロも自分の引き出しを全開にしている。M-1「Warped」やM-3「Deep Kick」、M-7「One Big Mob」などで聴かせる、ヘヴィなギターリフで押してからのクリーントーンやスローテンポで一気に落とす、という手法はまんまJane's Addictionのそれ。一方のフリーも負けじと、トレードマークでもある高速スラップやグルーヴィなベースフレーズなどを随所で発揮(M-2「Aeroplane」、M-5「Coffee Shop」など)、アルバムの至るところで、まるでケンカの如く互いに弾きまくるフリーとナヴァロの非常にスリリングなプレイを聴くことが出来る。
一方でM-4「My Friends」やM-9「Tearjerker」など、今まで作って来なかった王道バラードへの挑戦も見られる。アンソニーに関してはジョン復帰以降のボーカルスタイルの基本がここで出来上がっており、次作『Calfornication』(1999)以降のメロディアス路線へ繋がる要素を見せている。またこういったバラード曲で聴かせるナヴァロの泣きのギターなんかは、もしかしたら当時のジョンじゃ弾けなかったんじゃないかと思わせたりもする。
ちなみにコレ余談&個人的な印象なんだけど、レッチリって何かとメタラーから忌み嫌われてる感があるけど、そんな彼等にもこの『One Hot Minute』は評価が高かったりする。分かんないたまたま自分の周りにそういう人が多いだけなのかもしれないけど。
そんなこんなでガラッと印象を変えつつ生まれ変わったレッチリ。そんな彼等がドロップした本作は、セールス的には化物過ぎた前作を確かに下回ったし評論家からの反応も決して芳しくは無かったけど、それでもUSビルボード4位、売上枚数200万枚超えという好成績で発進、伝説の1997年第1回フジロックの嵐の中のライブだったりなど話題も事欠かず、再びグイグイな活動を続けていった…のだけれど、結局ナヴァロは本作のみの参加で1998年に脱退。レッチリと元ジェーンズの究極のコラボレーションは僅か5年、アルバム1枚で幕を下ろしてしまう。
結局その後にジョン・フルシアンテが復帰、翌1999年に『Calfornication』をリリース、これがBlood Sugar〜よりも売れてしまった結果、バンドは第二期黄金期に突入していくのであった…というのが、本作のあらまし。

…と、ここまでは良かったんだけど、後にこのアルバム、「アレは無かった事にしたい」とメンバーが発言、更にジョン復帰後のライブでは収録曲が一切セットリストに入れられないという、バンド側直々の黒歴史認定を受けてしまう。
そんな状態故か、レッチリファンの間でも評価が分かれ(特に純真なジョン主義者からはかなり冷遇されているとか何とか)、好評価しているファンも何故か「あんま大きな声で言えないけど実は…」感を露骨に出した上でフェイバリットに挙げたりと、なんか腫れ物扱い。
そんな前評判ばかり広がるもんだから、アルバムの完成度の高さに対して正当な評価が下されていない、或いは評価されても「一見さんお断り」なアルバムとして扱われている。
実際自分もそうだった。聴いた順番はかなり後の方だったし。まぁ一聴した瞬間にこれまでの聴かず嫌いを全力で後悔したワケですが。
多分この露骨な黒歴史扱いについては、アンソニーやフリーだけじゃなくて復帰したジョンの意向も幾分かあったんじゃないかと思われる。実際2009年にジョンが再び脱退してジョシュ・クリングホッファーに交代してからは「Aeroplane」とかはたまにライブで演奏してたらしいし。そらそうだ、何で元カノから貰ったアクセサリー未だに付けてんのよ、みたいな感じだもんね。或いはみんな歳食って拘りも薄れたか?
普通に聴けば非常によく出来たアルバムだし、まぁナヴァロ加入の影響が色濃いとは言えレッチリらしさも一応あるし、またジョン復帰以降推し進められていくメロディアス路線のプロトタイプのような楽曲もあったりと、実はレッチリ史に於いてはすごく重要な1枚じゃないのかと今では思っているのだけれど、前述のような黒歴史認定など、どうしてこうも評価が低いのか、というのをちゃんと考えてみると、色々と思い当たるフシはある。
一番の理由は、元々Red Hot Chili Peppersというバンドがギタリストに求めるものに対して、ただ単純にナヴァロはそれに当て嵌まらなかった、という事だと思う。
彼等のギタリストとしてのベンチマークはジョンでなく、初代のヒレル・スロヴァクなんだろうけど、演奏力は勿論の事、スタジオで「せーのっ」でジャムった時のノリや引き出しの多さ、要するに即興演奏のノウハウというのをバンド側は重視していた。実際今日のライブでも即興パートは当たり前に出てくるしね。
そしてジャムって出てきた素材を纏める過程においても、そもそもビビッと来る素材をいくつ引き出せるかなどのインスピレーションだけでなく、「こういう風に来たら、ココでこうして、こうだよね」みたいなアイデアに於いてもメンバーと合致する、というのが、レッチリというバンドがギタリストに求める最大の要素だった。それは単に音楽的素養やテクニックで培われるものではなく、いち人間としてどこまで互いを理解し合えるか、という事。
初代ギタリストのヒレルはメンバー云々以前にアンソニーとフリーの唯一無二の親友だったし、ジョンは元々バンドのファンとしてその様子を間近で感じ取っていただろうから、加入後すぐに馴染んで実践出来ていたけど、ナヴァロに関してはまぁ界隈近いから顔見知り程度には仲良かっただろうけど、正直そこまでの信頼関係とかは無かっただろうし。それに音楽を組み立てるアプローチに関しても、リフからジャムって広げるっていう基本的な部分はレッチリもジェーンズも同じだったんだろうけど、そこからの広げ方や纏め方に関して大きな違いがあった可能性は高い。Jane's Addictionの2ndアルバム『Ritual de lo Habitual』(1990)や、後のナヴァロのソロ作『Trust No One』(2001)などを聴いてみると分かるけど、前者の後半部分に見られる大作志向などは、瞬間的閃きなどでは作る事の出来ない、より客観的な目線と高度な計算力が無ければ作れない仕上がりになっているし、後者のソロ作で見られるインダストリアル寄りな世界観は、恐らくそういった方法論、要するに曲全体を見渡し、どんな音がどれ位必要か考えた上で組み立てる、みたいなアプローチで制作されたんだろうなぁ、という仕上がりになっている。
全てが直感的なレッチリと、より熟考・計算するナヴァロ。どちらが良い・悪いとかじゃなくて、単純にやり方が違った。
あと人間的な属性のようなものも違ったんだろう。レッチリって遊戯王で言ったら地属性だけど、ナヴァロなんかコテコテの闇属性だし。
もう1つは、このアルバムが良くも悪くも「時代性」というものを色濃く反映し過ぎてしまっている点ではないかと思う。
Red Hot Chili Peppersというバンドは、オルタナシーン出身でありながら、その後シーンとは適度な距離感を保ったポジションにいた。デビュー直後こそFishboneやJane's Addictionなどのバンドと共に、オルタナシーンにおいてミクスチャー・ロック黎明期を支えていたが、ワーナー移籍と『Blood Sugar Sex Magik』の大ヒット以降、リスナーやファン層はオルタナ界隈を主としておきながら、当時問題視されていたファンからの過剰な期待やメディアからのハイプなどとは無縁の立ち位置を築き上げる事に成功する。その絶妙な位置は、後にコートニー・ラブ(Hole)から「あのポジションが羨ましかった」と言われるほどだった。
実際、『Blood Sugar Sex Magik』というアルバムを改めてちゃんと聴いてみると、当時のグランジ・オルタナ界隈のバンド(例えばNirvana、Pearl Jamなど)が持つ空気感を微塵も感じさせない仕上がりになっている事に気付く。これはバンドに過剰に干渉しない、好きなようにやらせるリック・ルービンのプロデュース方針が成したワザでもあると思うが、結果的に「Give It Away」や「Under The Bridge」などの曲は未だにライブでのアンセムとして演奏されているし、アルバム自体もバンドの代表作として新旧多くのファンに愛されている。また日本国内においては未だに「ロックとラップ、と言えばレッチリ」みたいな認知をされ、ミクスチャーロックの名盤として今日まで紹介されている。
その一方で本作『One Hot Minute』はどうだろう。ナヴァロがもたらしたであろうこのダークな空気感はまさに90年代そのものである。本作を作っていた1994〜1995年という時期のアメリカでは、94年にカート・コバーン(Nirvana)がこの世を去り、次期シーンのリーダー覇権争いのような事が起きていた。オルタナ界隈からはPearl Jam、Nine Inch Nails、Alice In Chainsらが安定して君臨する中それに加えてSoundgardenやSmashing Pumpkinsらが参戦、シーンの外からはGreen DayやWeezerなどのポップパンク、パワーポップが急速に伸び始めていたり、その裏でKornが密かに胎動を始めたり…など、とにかく混沌としていた。こうやって字面に起こしただけでもゴチャゴチャしてるもん。あぁややこし。
カート・コバーンは元々レッチリメンバーとは親交があったし、それに加えて同じくメンバーの友人だった俳優のリヴァー・フェニックスの死(1993年)なども、本作に大きく影を落とした(M-13「Transcending」はリヴァーに、M-9「Tearjerker」はカートに、それぞれ捧げられている)。他にもこの頃アンソニーが再びドラッグにハマり出しちゃったりなどの要因もあるけれど、そういった影が、ある意味90年代ド真ん中でその空気感に染まり切っていたデイヴ・ナヴァロという男を招聘した事によって、結果的に「時代性」という形でサウンドに大きく反映されてしまった格好となった。やっと誰の目も時代の流れも気にならずに好きな事が出来る立ち位置に来てたのに、時代のド真ん中に戻っちゃったじゃないか。どうすんだよこれ。
レッチリのディスコグラフィーを順に並べた時、本作だけ異様な浮き方をしているのは、単にナヴァロのせいだけではなく、そういう理由もあるのだと思う。そして外部からの影響を受け過ぎてアルバムをこういった方向に持っていってしまった事、大袈裟に言えばバンドのアイデンティティを危機に晒してしまった事への反省が、1998年のナヴァロ解雇(最終的な決め手はドラッグだったらしいけど。後述)とジョン再招聘の一因となったのではないか、と何となく推測してみる。

そんなこんなで「本当にこれで良いのか?」となったアンソニー・フリー・チャドの3名。その頃辞めていったジョンがクリーンになって再びメンバーと連絡を取るようになってたりとか、反対にナヴァロはドラッグ依存が悪化していったりなんて要因も重なり、前述のナヴァロ脱退とジョン復帰となった。
ジョンが再びバンドに戻ってからというものの、レッチリは従来のファンク路線も踏襲しつつ、よりメロディアスな「大人なロック」を志向していく。それはバンドを離れていた間に壮絶なドラッグ依存とその治療を経験したジョンだけでなく、アンソニーやフリーもこの『One Hot Minute』で変なヒートアップのしかたをしちゃったから、それが冷めた後にものすごい脱力感あったんじゃないかなぁと、なんとなく予想しながら、久々にこのアルバムを聴いた。
【好きなアルバムについて語る】YUNGBLUD - 21st Century Liability

先日Bring Me The HorizonとコラボしたYUNGBLUDさん。その話題性というか、何かと目に付くその立ち振舞いから存在自体は知っていたけど、今回初めてアルバムをちゃんと聴いてみた。
せっかくなので感想を文章で残しておきます。
良い意味で色々と裏切られました。
【若気の至りの目指す先は】
2018年リリース。イギリスのシンガーソングライター、YUNGBLUDのデビューアルバム。
いきなりだけどこのYUNGBLUDというアーティスト、シンガーソングライターって呼ぶのなんかすごい抵抗ある。まぁ本当に、本名ドミニク・リチャード・ハリソンというシンガーソングライターが、アーティスト名義としてYUNGBLUDと名乗っているので、紛れもなくシンガーソングライターなんだけれども。ただそのアートワークやアーティスト写真、ライブ映像などを見て頂ければ、私の感じているこの得体の知れない抵抗感も、何となく分かって頂けるのではないかと期待している。
YUNGBLUD…「血気盛んな若者」を意味する"Youngblood"という言葉が由来であるが、アートワークやポートレイト、ライブパフォーマンスや言動など、全てにおいて「若気の至り」を地で行くようなスタイルが目に付く。中性的なメイクアップ、ド派手なヘアスタイル、奇抜な衣装。ライブやPVでは時にヒステリックな表情で叫び声を上げ、平気で自らの顔に血糊を塗ったくる。その姿は1970年代半ばのグラムロック〜ロンドンパンク的スタイルを彷彿とさせる、現代ではすっかり珍しくなったもの。本人も自身のルーツとして、The BeatlesやThe Rolling Stones、The Crash、Sex Pistolsなどの名前を挙げていた。
どうでも良いけどこういう見た目って、4〜5人のバンドでやられると正直若干ウザいけど、1人だけでやってくれると楽しく見てられるね、まぁどうでも良いんだけど。
そんな若気の至りを地で行くYUNGBLUD、そんな前情報ばっかりが入ってくる中でいざアルバムを聴いてみたら、大方は立ち振舞い通りの音絵巻を広げるが、時に良い意味でギャップのあるアプローチも多い。
特に驚いたのが、リズムに現代R&B、ヒップホップ・トラップ的な電子的ビートが多用され、そこを中心にエモ・ラップ的歌い回しとか都会的なシンセサイザーとかの色んな音が乗っけた、とにかく情報量の多いサウンドなんだけど、そんな楽曲群の根幹を成すのはまさかのレゲエという点。これはちょっと予想外だった。まぁレゲエと言っても、例えばThe Specialsとか後期The Clashとか、最近だとSKINDREDとかの、あくまで「非ジャマイカ人によるレゲエ」を、しかもデジタルで構築してるという事で、純ジャマイカ産レゲエと比較するとかなりアク抜きされてる、というかほぼ無味無臭感は否めないのだけれど。
他にもプロダクション面に目を向けると、ベーシックトラックの大方はProToolsとか使って打ち込みで作られてるんだろうけど、ヒップホップやEDMなどが陥りがちな、自然由来成分0%のような人工的過ぎる質感という事はない。デジタルなトラックと相反するような、プライベートな苦悩を曝け出した歌詞と、イギリス的なアンニュイなメロディラインが混ざった結果、掴めそうで掴みきれない、分かりやすいようで奥深い、独特のサウンドを編み出している。最新テクノロジーにはふんだんに頼りつつも、あくまで曲の基本はちゃんとギターもしくはピアノで作ってるんだろうな、という暖かみとシリアスさが感じられる。
現在のUKロックシーンの基盤というか主流というかがいつ出来たのかを遡ると、やっぱりOasisに辿り着く。
まぁもう少し辿るとThe Stone RosesとかThe Smithとか、更に辿るとU2、行き着く先はThe Beatles…ってなっちゃうのだけれど、最終更新履歴的な意味で考えてみると、やっぱりOasisらへんなのかなぁって個人的には思っている。
Oasisを筆頭とした所謂ブリットポップムーヴメントによって、「UKロックっぽさ」みたいなのの基本フォーマットが出来上がり、以降多くの行進アーティストによってなぞられてはいるが、逆に言えば二番煎じ三番煎じが進んでいき、結果どんどんローカル性を増していったUKロックは、いつしか世界、というかアメリカ市場への影響力を失っていった。
勿論ブリットポップ以降でも、ColdplayやGorillaz、最近だとThe 1975やBring Me The Horizonなど、世界的成功を収めたイギリスのバンドは存在するものの、どれもUKロックのフォーマットからは外れたところにあり、UKロック原理主義者からは冷ややかな見られ方をされているのも事実である。
今思うとThe 1975の登場って、膠着し切ったUKロックシーンに対しての挑発だったんだなって思う。
労働者階級出身、モッズコートなどのカジュアルな服装に革靴、ボサッとした髪、ギターのピックアップはシングルコイルかP-90でジャキジャキした音…みたいな、よく言えば伝統的、悪く言えば古臭いUKロックのフォーマットに対して、80年代型ポップスからトラップまでを飲み込んだ、ワイドな視野で洗練されたスタイリッシュなサウンドと、それに相反するようなリアルな苦悩を過激な表現で曝け出した歌詞、見るからにヤニ臭い・酒臭い・クスリ臭い、危険なオーラを放ったMatthew Healy(Vo.)の存在感…などは、フォーマットをなぞるだけでリアルさを失くしたUKロックとは全てにおいて対極に位置していたし、そしてそれは現在絶滅危惧種とも言われる「ロックスター」像をしっかりと再現したものだった(Matthewが以前『俺はRadiohead派だ』と発言したのも、テンプレ化したUKロックを揶揄する意味もあったのではないか、というのは考え過ぎか)。
YUNGBLUDが目指しているのは、Matthew HealyがThe 1975と共に成し遂げた「ロックスター像の復権と再構築」であり、それをThe 1975よりもっと自由、悪く言えば無秩序なアプローチで目指しているように見える。
とにかくクールだと思ったものは貪欲に取り込み、気に喰わないモノにはとことん噛み付いていく。そして彼のルーツであるロック・パンクアーティストの様に、現代ロックのセオリーを徹底的に無視した創作スタイルと、ジェンダー観を初め既存の価値観に対してとことん挑戦していく立ち振舞いは、本作以降より過激さを増していく。
そんな姿が業界内でも話題となり、Machine Gun KellyやHalsey、Marshmelloなど幅広いアーティストとのコラボも積極的に行っているなど、イギリスという枠を超えた活動を展開するに至っている。
現在の主なマーケットとしては、先述のコラボのメンツ的にもイギリスよりはアメリカ中心なんだろうな、と想像。まぁ似たような方向性を目指してるBring Me The Horizonも今や完全アメリカに照準合わせてるし、今のところこの手の音楽性なら「アメリカで受け入れられたならイギリスもイケる」な流れに全体的になってる感あるし、Machine Gun Kellyみたいなヒップホップアーティストへの接近(ちなみにこのコラボ、背後にはTravis Barkerもいる)は、ロックはあくまでメインストリームで闘えるという事を証明しようとしているに他ならない。
ただこう言った彼の立ち振舞いも、ある意味若さ故のエネルギーというのが必要不可欠であろう事は想像に難くない。鬱もフラストレーションもごった煮して、こういった形で爆発させるには、やはり若さというガソリンが絶対的に必要なのだ。まだ20代前半だと言うが、ある程度年齢を重ねた先にどのような姿を目指しているのかが現時点では全く見えないのが、楽しみな点であり同時に不安な点でもある。かつてパンクが初期衝動をすり減らし切った先に、その後進む為のエネルギーを見出せず消滅していった歴史があるように、彼も何かのタイミングで息切れしてしまわないかが少し心配。
…っていう意識は多分本人の中にも多分あるだろうけど、結局はそんな深く考えてない可能性の方がデカいかも。
それこそYUNGじゃなくなった暁には、かつてDavid BowieがZiggy Stardustを葬ったように、YUNGBLUDという名前もあっさり捨ててまた別の名前でも名乗り出したりして。
もう既にここまで振り切ってるのならそれくらいやってくれないと面白くないかも、なんてね。
2019年を振り返る 〜今年聴いたアルバム編〜
ついさっき、
2019年を振り返る 〜バンド編〜 - A Confession of a ROCK DRUMMER
を書いたばかりだけど。
こっちでは【今年聴いた新譜を振り返る】という、言わば完全に自己満足な記事を書いてみようかと。
というのもコレ、結構前から温めていたのがようやく纏まったから、年明けギリギリに上げちゃえ、と。
どこまで行っても根本はただの音楽好きなリスナーなんです、ワタシ。
…多分後で恥ずかしくなって消すやつやんこれ。
まぁ、興味ある方はお付き合い下さい。
Bring Me The Horizon - amo

2019年1月25日リリース。英国シェフィールド出身の5人組Bring Me The Horizonの6作目。
今年聴いた一番最初の新譜。2019年ロックシーンの台風の目になったんじゃないか、という1枚。
前作『That's The Spirit』(2015)で最新型スタジアム・ロックバンドへと成長したBMTH。「でも次はどうするのかな?」と注目してた中でのリリース。
トラップへの接近や、アンビエント的エレクトロサウンドの強化などはしてるけど、あくまで前作で築き上げた路線をベースにしてるって感じ。
特筆すべきはOliver Sykes (Vo.)の歌唱力が飛躍的成長を遂げた事。来日公演観に行った時も思ったけどめっちゃ歌上手くなっとる。彼の歌唱力向上も本作を補強する大きなファクターであるのは間違いない。
きっと彼等の今後のキャリアにおいて、ある種「過渡期」的立ち位置にいるアルバムなんだろうな、と。次回作、また更に次のアルバム…とリリースされた後に今作を聴くと、また違った聴こえ方がしそう。
そういう意味でも楽しめる1枚。
このバンドのディスコグラフィを改めて1枚目から追ってみると、結構面白い。
アルバム毎に路線は変えつつも、全てが地続きと言うか、ちゃんと1本の線で繋がってる。
バンドとして正しい段取りを踏まえた上での今なんだなと。もしかしたら1枚目を出した段階で、もう今の姿がボンヤリ見えていたんじゃないかとすら思えてくる。
その辺のセンスというか、やっぱり凄いバンドだなと。
Sticky Fingers - Yours To Keep

2019年2月8日リリース。オーストラリアで国民的人気を誇るロックバンド、Sticky Fingersの4作目。
レゲエを下地にしつつヒップホップ、サイケデリックを取り入れたアイリーなサウンドでデビューした彼等。本作はDylan Frost(Vo.)の療養の為の活動休止を経た後初のアルバムになるとか。
1曲目「Sleep Alone」から分かる通り、サイケ色は一切無くなり、温かみと哀愁を全般に漂わせたオーガニックなサウンドを志向している。広々とした草原や、深い森の中などを想像させる音像、そして生命賛歌のように響くディランの歌。スティフィらしくないっちゃらしくないのかもだけど、大人の階段を一歩登ったかのような姿に感動する1枚。
正直、ワールドワイドな説得力を持ったアルバムじゃないけど、ローカルに特化した温かさや、シンプルながらも手の込んだアレンジやサウンドが染み渡る。
今年一番リピートしたアルバムかも。
While She Sleeps - So What?

2019年3月1日リリース、先程書いたBring Me The Horizonと同じ英国シェフィールド出身のメタルコアバンド、While She Sleepsの4作目。
前作『You Are We』(2017)が傑作だったのと、1月には待望の来日を果たしたりと個人的にも期待していた1枚。
作品を追う毎にクリーンパートのメロディアスさが増してきてた彼等だけど、今作ではメロディアスさはそのままに、より初期衝動全開のハードかつシャープなメタルコアサウンドを前面に押し出している。
スクリーム担当のLozも、部分的ではあるけどクリーンを歌っているけど、激しいパートではよりハイピッチなスクリームを聴かせてくれる。
今時こういう気持ち良さを感じさせてくれるメタルコアも少ないよなぁ。
Suchmos - The ANYMAL

2019年3月27日リリース。
今日の日本のシティポップブームの火付け役とも言えるバンド、Suchmosの3枚目。ちなみに自主レーベル立ち上げ後1発目のフルアルバムとな。
とは言え本作、「Stay Tune」などのアーバンなシティポップを鳴らしていた頃の彼等とは別物の、60年代後半以降のサイケデリック・ブルースロックを彷彿とさせるサウンドに。
その空気感は60年代後半のあの時のバンド達が持っていたそれのまま。でも単なる模倣に終わらず、ちゃんとルーツを理解した上で昇華している感じ。
1曲1曲が長いし抑揚も少ないので、しっかり聴き込もうとすると眠くなってしまうけど、全身の力を抜いて、ちょっとお酒も飲みつつテキトーに流し聴きすると良い感じにフワフワ出来る。もうちょっと聴き込んで隅々まで理解したいけど、きっとそういう聴き方は向かないアルバム。サイケってそういうもん。
Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

2019年3月29日リリース。
"2019年の顔"とも言える人、ビリー・アイリッシュの1stアルバム。
いやー話題になったねコレ。各メディアや様々な大御所アーティストからの絶賛を受けてる彼女。正直「ハイプじゃね?」と一瞬思ったりもしたけど、内容的には絶賛の嵐も納得の1枚。
最新型EDM・トラップサウンドをベースにしたダークかつチルい世界観のトラックに、露骨に眠そうなボーカルを乗せるという、までありそうで無かった形。更に"ルーツが見えにくい"そのスタイルがミステリアスさを生み出している。ただし聴くとその日1日分のやる気を根こそぎ持って行かれるので注意してされたし。
怖いのは、このアルバムのトラックはほぼ全て宅録で作られてるらしいって事。それで天下が取れちゃう時代。恐ろしいわぁ。
まだ読んでないけど、ロッキングオンの2019年アルバムランキング、多分1位。笑
…なんかコレだけすごく雑に書いちゃったな。
Perry Farrell - Kind Heaven

2019年6月7日リリース。
Jane's Addictionのボーカリストにしてロラパルーザの創設者、90年代オルタナの大ボス、ペリー・ファレルの2枚目のソロ。
最初リリースされてたの知らなくて、知った時はめっちゃ驚いた。まさか聴けると思ってなかったし。
その音は何とも形容しがたいんだけど、聴けば分かる、どこもかしこもペリー・ファレル節全開。もう御年60歳、もう若き日のハイトーンもさすがに出ないけど、その歌声の持つ不思議な魔力は健在。そして作り出されるサウンドから滲み出る、何とも言えない"大人気なさ"。
これこそが彼の真骨頂なんだと思う。「いくつになってもやりたい事遠慮なくやっちゃいます!」みたいな。さすが90年代の大ボス。脱帽。
サカナクション - 834.194

2019年6月19日リリース。
サカナクションの7作目のアルバム。
なんと前作から6年ぶりのアルバムなんだそう。その6年間の間のバンドの音楽的変遷を網羅しつつの現在の姿を記録した2枚組。
「新宝島」に代表されるポップなDisc1、新曲「ナイロンの糸」に表れるシューゲイザー的ダークなカラーで統一したDisc2という内容。山口一郎氏(Vo.Gt)のインタビューを読んでみても、「これが新しいサカナクションです!」みたいな感じではなく、「とりあえず色々やった結果こんな感じに今のところ行き着いてます」みたいな暫定座標的な作品なんだろうな、と。
シンセの音もギターの音も、メロディラインもどこか昭和っぽくて、新しいのに懐かしい、レトロフューチャーな楽曲が多く揃っているけど、どの曲も"音の隙間"の活かし方が上手いなあという印象。所謂流行りのシティポップっぽい曲もあるけど、「ちょっと茶化してる?」みたいなアイロニーを感じてしまうのは気のせいだろうか。
Feeder - Tallulah
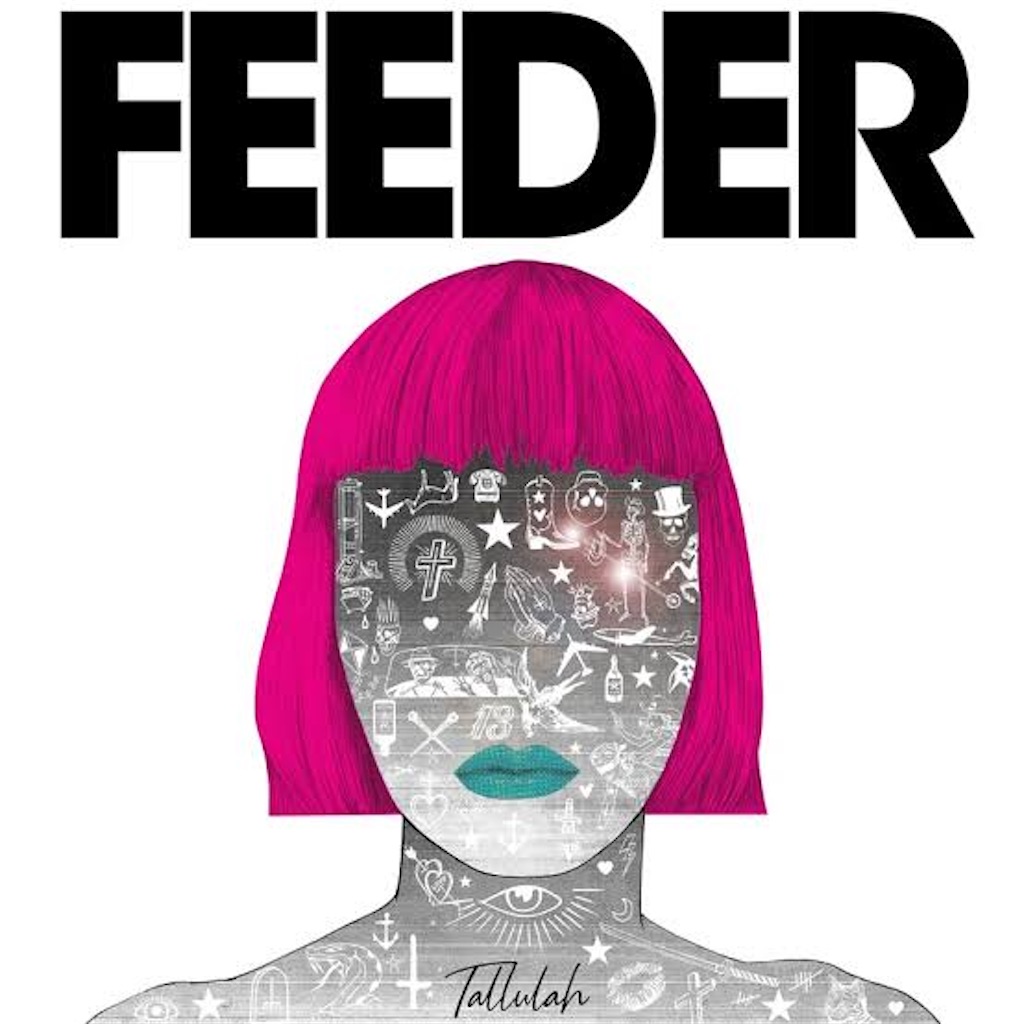
2019年8月9日リリース。
日本人ベーシストTaka Hirose擁する、英国の国民的ロックバンドFeederの10作目。
リリース自体も、その内容も、その後のジャパンツアーも含む全てが「待ってました!」な1枚。
最初から最後まで、全てがFeederらしい。前作『All Bright Electric』(2016)が、Grant Nicholas (Vo.)のソロ活動の影響が色濃く出た老生し切ったサウンドだったのに対し、今作はまるで若返ったようなフレッシュな作風に。実験的だった前作も面白かったけど、やっぱりこういう音が聴きたいな、という願望を見事に叶えて頂きました。
結果的にやってる事は王道Feeder路線なので、変わり映えっていう点ではしないけど、「だがそれが良い」って心から言える作品。
渋谷Quattroでのライブは最高でした。一生ついて行きます、Feeder。
Robbie Robertson - Sinematic
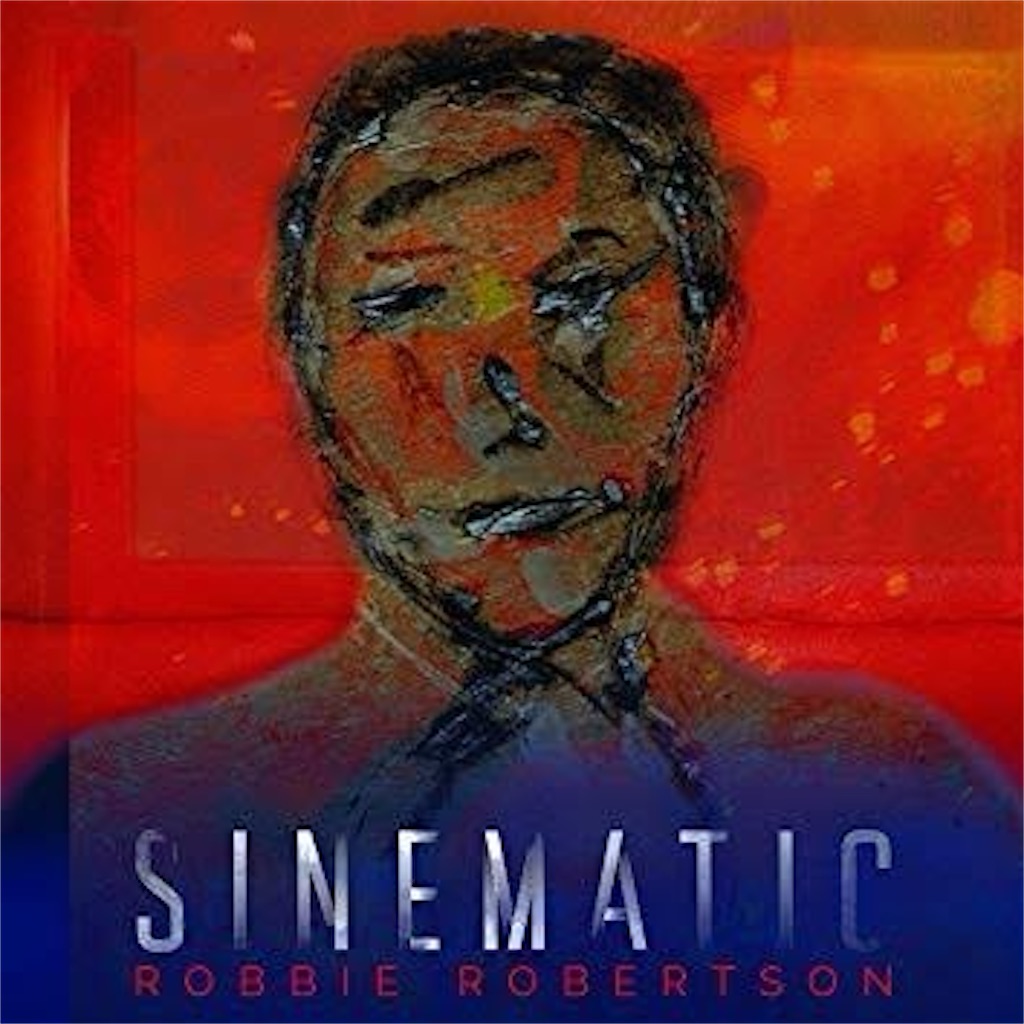
2019年9月20日リリース。
かつてはボブ・ディランのバックバンドとして活躍し、ディランから独立後、アメリカのロック史に大きな足跡を残した伝説のバンド、The Bandの元ギタリスト、ロビー・ロバートソンの6作目。
リリース日に偶然タワレコにて展開されているのを発見、父がThe Bandの大ファンなのもあって(勿論僕も好き)、ちょっと聴いてみるかと完全予備知識ナシで聴いてみたらとても良かった1枚。こういう時にサブスクって超便利。
The Band時代から脈絡と続く、太く柔らかい、オーガニックなロックサウンドと、湿っぽいジメジメした暗い空気感。物語性のある難解かつ殺伐とした歌詞。曲だけでなくコンセプトも掘り下げ甲斐のありそうな奥深い作品。
Robert Glasper - Fuck Yo Feelings

2019年10月3日リリース。
モダンジャズ界の若き巨匠(41歳。言うてそんな若くないけど笑)、ロバート・グラスパーの新作。この人はRobert Glasper Experimentとしてもアルバムを出してるので、通算何枚目ってのが正直数えづらい。笑
純粋な新作としては2016年、Experiment名義での『ArtScience』以来という事になるのか。
それまで、どんなアプローチでも基本的には高品質なポップスになるような作品を作り続けたロバート・グラスパーだけど、本作はメロディらしいメロディは皆無、とにかくリズムへの徹底的な追求のみに拘ったような内容。随所に飛び出す「Fuck」という言葉が意味するものとは。
まだちゃんと聴き込めていないけど、今年聴いた中では飛び抜けて実験的な1枚。しっかり理解するには、まだまだ時間がかかりそう。
Dylan Frost - Lush Linguistic

2019年12月6日リリース。
先に触れたSticky Fingers のボーカリスト、ディラン・フロストのソロ作。
割と唐突にリリースされて驚いた記憶がある。てかいつの間に作ったのコレ、みたいな。
8曲入りEP、ってのが公式の扱いらしいけど、トータル収録時間は40分しっかり超えてるので事実上フルアルバム。
内容的には2nd〜3rd期のスティフィに近いけど、より都会的な音像というか洗練されてる印象。
サイケなはずなのに色彩感がやや乏しい感じが、夜に都会の街並みを歩きながら聴くのにとても良い。
ちなみにApple Musicだと全曲にEマークが付いてるのがディランらしい。歌詞ちゃんと読んでみたい。
もうちょっと聴き込んでからちゃんとディスクレビューしてみたい1枚。
The Who - WHO

2019年12月6日リリース。
まさか本当に聴けると思わなかった、The Whoの新譜。ある意味今年一番のサプライズリリース。
前作『Endless Wire』(2006)をよりシンプルに、ブラッシュアップした感じで、音楽性的には王道フー路線から大きな変化はないけど、随所に昨年出たロジャー・ダルトリー(Vo.)のソロ『As Long As I Have You』(2018)との連続性を感じさせる部分もあったり。
ほぼ正式メンバーなピノ・パラディーノ(Ba.)とザック・スターキー(Dr.)が、今回は全面参加してるのが嬉しい。ピノの太いベース、キース・ムーンを彷彿させるザックのドラム、絶妙な浮遊感を醸し出すピートのコーラスワーク、ロジャーのソウルフルな歌…と、今のThe Whoに自分が求める全てが聴けて大満足。
Bring Me The Horizon - Music To Listen To~Dance To~Blaze To~Pray To~Feed To~Sleep To~Talk To~Grind To~Trip To~Breathe To~Help To~Hurt To~Scroll To~Roll To~Love To~Hate To~Learn Too~Plot To~Play To~Be To~Feel To~Breed To~Sweat To~Dream To~Hide To~Live To~Die To~Go To

2019年12月27日リリース。
Bring Me The Horizonが突如リリースした謎のアルバム。
いやこのアルバムは本当に謎。まずメンバーの演奏がオリバーの声以外恐らく出てこない。多分参加すらしてない。あとタイトル長い。
Todd Rundgrenの迷作『Initiation』(1975)のB面を彷彿させる。全体的に映画の挿入歌みたいな曲ばかり入ってるんだけど、構成音の一部が既に発表した曲のメロディや、同期のシンセパートとかから引っ張ってきたりとかしてるので、「この曲のコレってあの曲のアレじゃない?」みたいな聴き方したら楽しそう。結構集中力使いそうだけど。
しかし、一体どういう意図でリリースしたんだろう?
…良いお年を。